二重の堀、総計6つの堀に囲まれた芳賀氏の居城〜飛山城(とびやまじょう・下野(栃木))
二重の堀に驚愕!堅固な城であることよ。。
こんにちは、シンです。
2023年6月4日(日)。
栃木県宇都宮市にある、飛山城(とびやまじょう・下野)を訪れました🚙
この城は宇都宮氏の家臣・芳賀氏(はがし)が居城としていたものです。

◉城のジャンル
平山城(ひらやまじろ)
◉文化遺産としての見どころ
◉防御施設としての見どころ
◉駐車場所
『とびやま歴史体験館』前におよそ30台分ほどの駐車スペースあり

こちらの駐車場にまずは車を停め、

目の前にある『とびやま歴史体験館』から、まずは訪れました。

中には、甲冑や屏風などが飾られていたり、
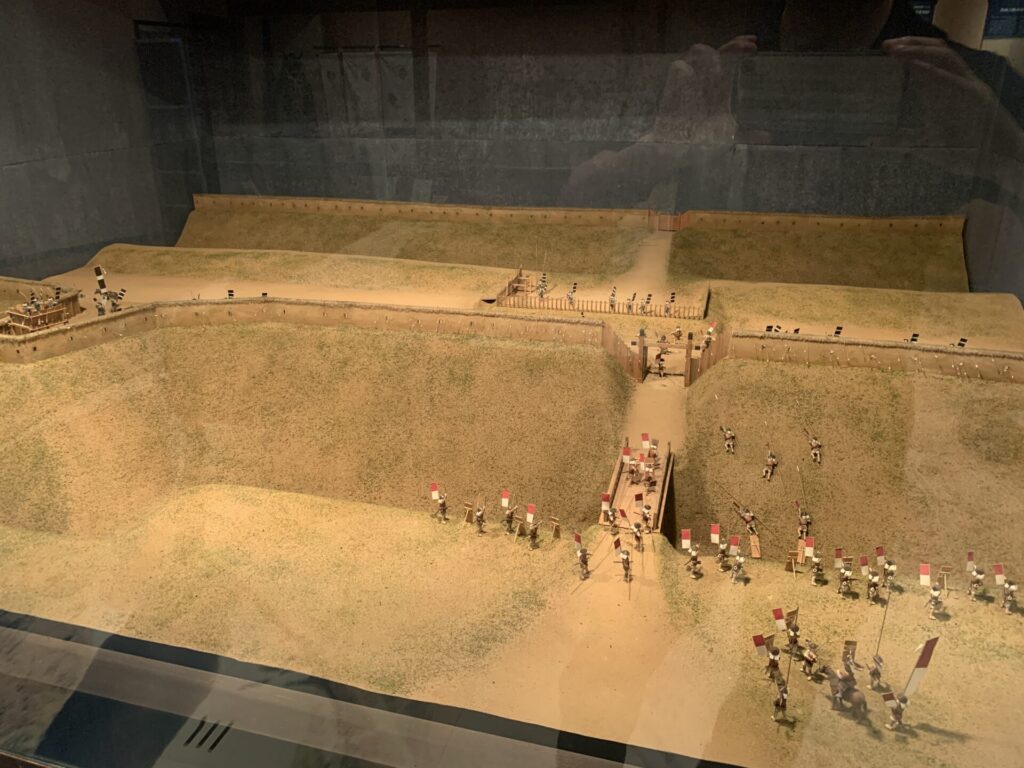
このように、城の防御施設が分かりやすく展示されています。
これは橋を渡る敵兵に対し、側面から矢を射かける、『横矢掛かり』というものです。

展示物を鑑賞後、
さっそく飛山城跡を探索します✊

(かなり日陰になってしまい、見づらくてごめんなさい💧)
飛山城は(見にくいですが)東西南北を合計6つの堀に囲まれた、かなり堅固な城であり、
しかもそれぞれの堀が、程度の差こそあれ、しっかり形をとどめているのです!

まずは、この木橋を渡り、飛山城探索の旅に出ます。
この木橋の下にあるのが、6号堀です。

側面から撮影すると、このように見えます。
くっきりと形が残ってますね。
いや、この日もそうでしたが、草刈り作業をされていた方々がいらっしゃいました。
遺構を残そうとする方々がいるおかげで、この城マニアも楽しむことができます🙇

こちらが、木橋を渡ってから撮影した土塁跡です。
奥の方に、草刈りをされていた方々が休憩していました。

さらに、6号堀を見下ろすように、櫓台が設置されていたとか。。
復元されたその櫓台からの眺めを動画でご覧ください。
6号堀はこの櫓台の位置から見下ろすと、
角で大きく曲がり、先ほどの木橋の位置まで長く続いています。

土塁を降り、
さらに内側の土塁の上に登って撮影したのがこの写真です。
こちらは5号堀です。
ここまでで、すでに二重の堀が敵兵の進軍を阻むわけです。
ここも、土塁の上から動画撮影しました。ご覧ください。
手前に木が多く、堀の様子を把握しにくいですが、
こちらもかなりしっかりと形が残る5号堀です。
そして、この5号堀を渡る手前に枡形虎口(ますがたこぐち)が待ち構えています😱
枡形虎口(ますがたこぐち)も分かりやすく存在感を示す!
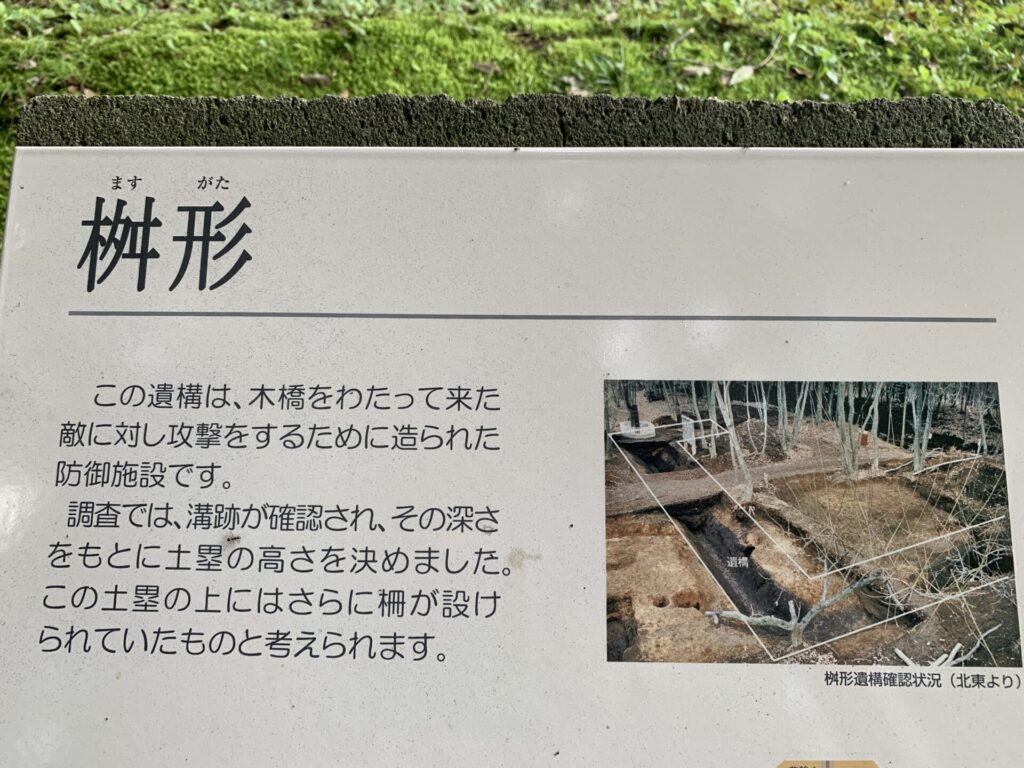
この説明板には「枡形(ますがた)」としか表示されていませんが、
枡形虎口(ますがたこぐち)のことでしょうね。
枡形虎口(ますがたこぐち)とは、、城兵の城への出入り口であり、
かつ、敵兵が簡単に攻め込めないように、わざと通路を折れ曲がるように造り、
正面からだけでなく、側面からも城兵が攻撃を仕掛けるようにしたもの、です。

ご覧のように、左手前の橋を渡る敵兵は、
左奥の方に折れ曲がるようにして進むしかなく、
その間に、正面と側面の土塁上から攻撃を受けるわけです。

枡形虎口(ますがたこぐち)を突破できたとしても、
まだまだ城の防御施設が待ち構えています。

こちらの門を通過し、
さらに城内へ進んで行きます。
北から城の中央部にかけて1号、2号、3号堀が行手を阻む!!

城跡の中央部に進むと、
前方に建物が見えてきます。

『堀立柱建物』でした。
主郭(本丸)を防御するための将兵の待機所だったようですね。

入り口はこのような。。
屋根の上の石が、それっぽく戦国の世を表しているようで、風情を感じます。

こちらが、中の様子。
靴を脱いで、お邪魔することもできます。

この『堀立柱建物』はこのように複数あり、
結構な広さの敷地内にあったことが分かります。

その敷地(曲輪Ⅳ)の北側を覆うのが2号堀です。
この2号堀もまた、見事な造りをしています。
こちらも動画でご確認ください。
くっきりとL字型に折れ曲がり、
この堀に敵兵が落ちようものなら、
複数の土塁の上・側面から狙いうちされるのは間違いなさそうです😱

そして今度は北側に向かいます。
次に、城の最も北側を防御する1号堀の様子を、こちらも動画でご覧ください。
これまでの堀に比べれば、かなり浅めで、
ぱっと見には、堀と判別しにくいですが、、。

今度は3号堀です。
こちらは城の北西部からやや中央に伸び、
この方角からの敵兵の侵攻を阻んでいます。

こちらも、復元せずに当時のままとしているためか、
かなり浅めで、ほとんど堀とは判別できません。

城の北西部に到達、ここから今度は南側に進んでいきます。

城の西側には、このように鬼怒川(きぬがわ)があります。
こちらは西側の天然の防御線だったのでしょうね。
4号堀もまた、敵兵を狙い撃ちする「キルゾーン」!!
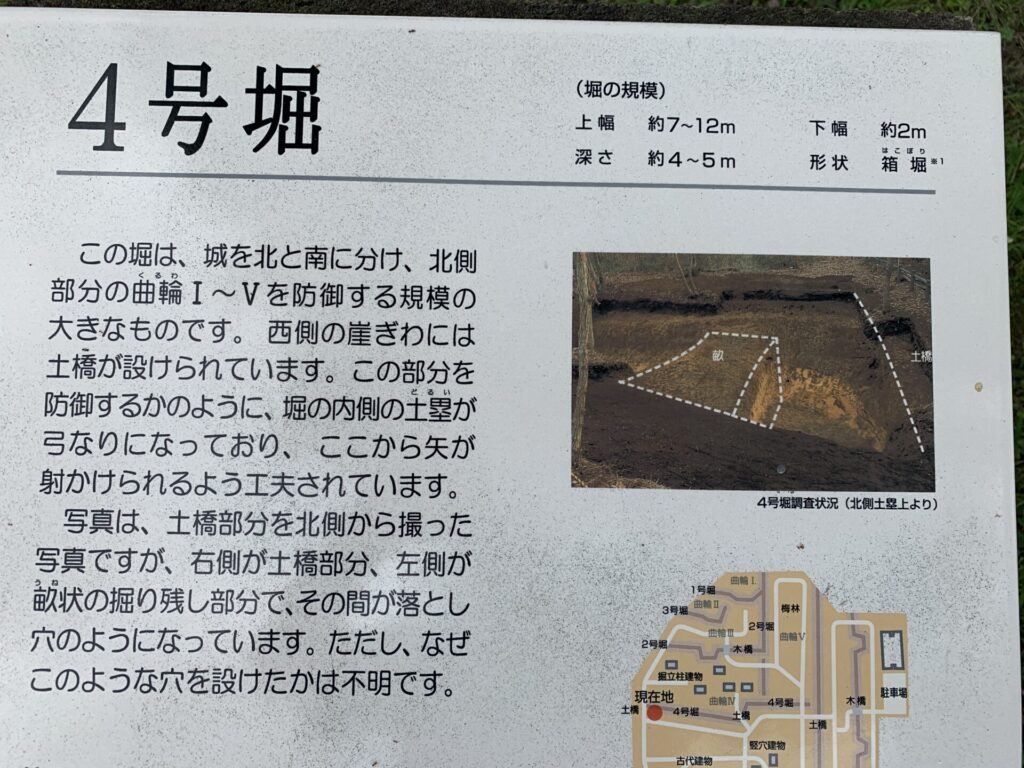
城の西側、ほぼ中央部に4号堀が大きく存在感を放っています。
土橋を渡る敵兵を側面から攻撃しやすくなるよう、土塁が屈曲しています。

この4号堀もまた、見事な形を見せてくれています。
手前の掘り残し部分は不明と、説明板にありましたが、
北条家の得意技術、「障子堀」を思わせるようです。
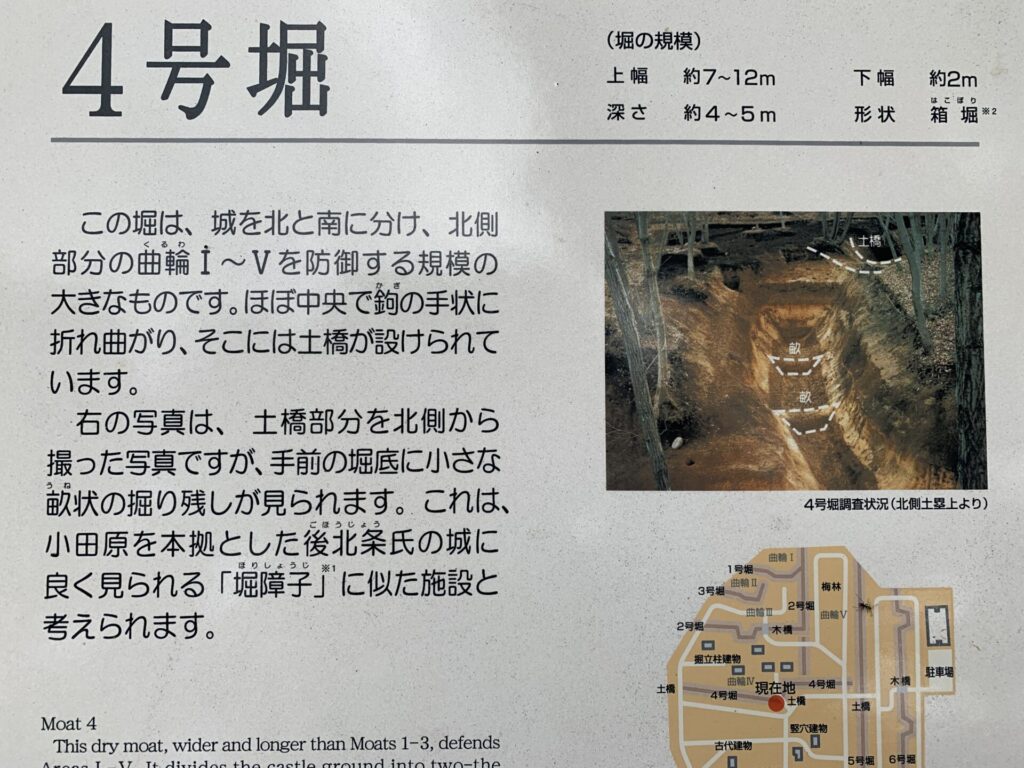
と、少し歩いたところにまたも4号堀の説明板が!!
こちらは、しっかりと「障子堀」について触れているじゃないですか!
それでは、この4号堀も動画に収めましたので、ご覧ください。
これだけ土塁が湾曲していると、
敵兵も攻めにくいでしょうね。。
四方八方から狙われているようで、生きた心地もしないでしょう😅

次に、もう少し南に進んでいきます。

前方に、また違う建物が見えてきました。

こちらは、古代の竪穴建物のようです。
城としての古さというか、歴史を感じます。

その竪穴建物から道を反対側に進むと、
こちらにもまた違う形の建物が見えてきます。

こちらは、同じ竪穴建物でも、中世のもの、だそうです。
当時は、地下に降りて入る、みたいな造りだったのでしょうか。
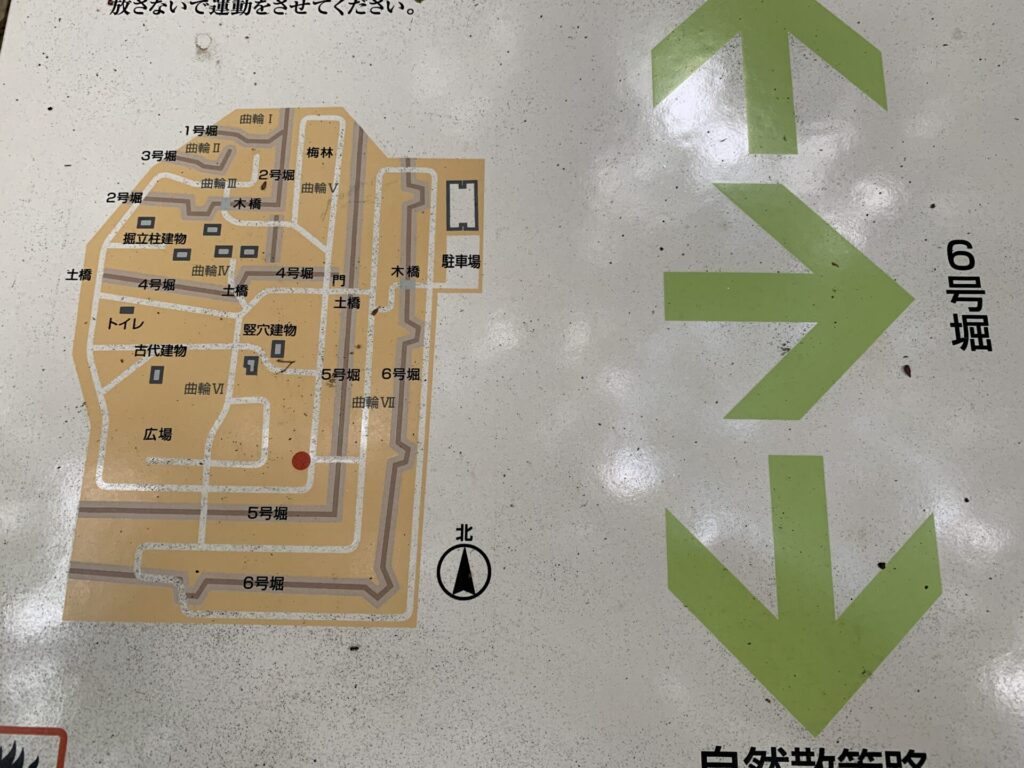
竪穴建物群を後にし、
城の南東部までやってきました。
再度、5号堀、6号堀を目にして帰ります。

それにしても、見事な堀の数々、
その防御施設の堅固さには恐れ入りました🙇
それほど標高がない平山城であっても、
このように多くの堀を巡らすことで、「キルゾーン」を容易に準備できるものだと、
つくづく感心させられます。
皆さんも栃木県を訪れる機会がありましたら、一度立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
ではまた!!
👇宇都宮城についての記事はこちら👇












