井楼矢倉に角馬出、比高二重土塁を備える、土城マニア必見の城跡〜逆井城(さかさいじょう・下総(茨城))
まず目に飛び込むのが、存在感のある二層櫓
みなさん、こんにちは、シンです。
2023年7月9日(日)。
外にいると嫌でも汗が噴き出る真夏日に、”城攻め”しちゃいました😅
茨城県坂東市にある、逆井城(さかさいじょう・下総)です🚙

◉城のジャンル
平城(ひらじろ)
◉文化遺産としての見どころ
◉防御施設としての見どころ
◉駐車場所
逆井城跡公園駐車場に10台分ほどの駐車スペースあり
近くまで行くと、『逆井城跡公園』の看板が見えたりしますので、
まずそこまで迷うことはないかと思います。

こちらが逆井城跡公園の駐車場です。
この写真の右側に城跡があります。
というか、駐車している時点から、櫓などが見えます😀
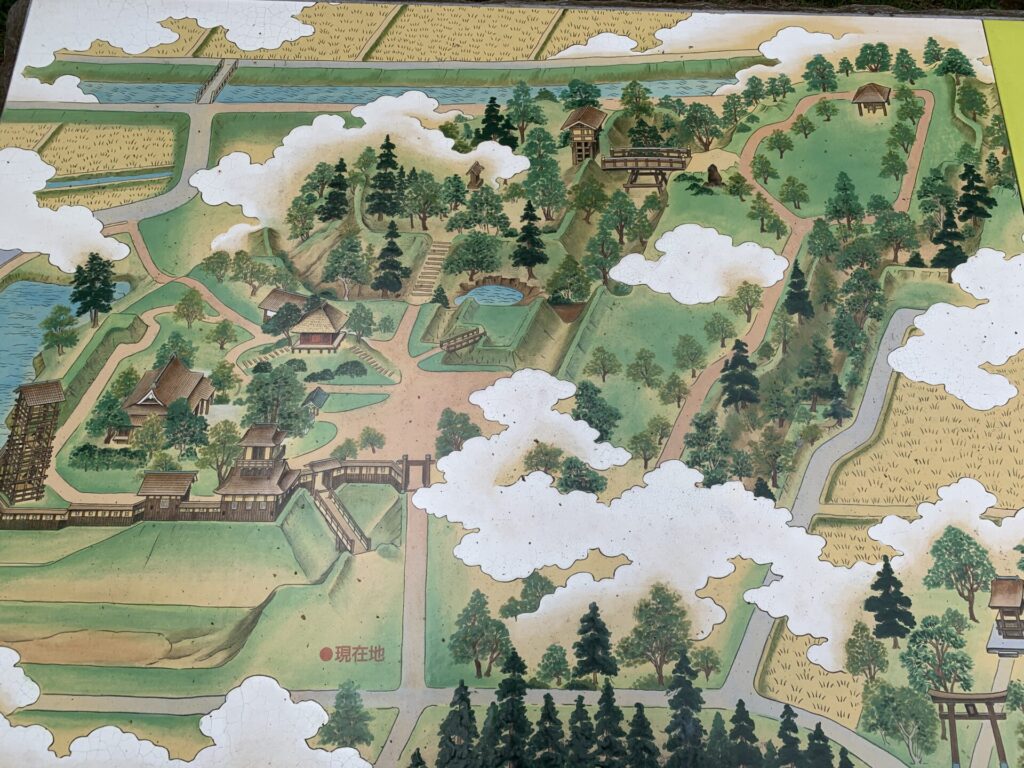
これが城の縄張り図です。
縄張り図というほど、詳細な情報はありませんし、単なるイラストに見えますが、
それでも城跡のおおよその見取り図ということは言えます。
逆井城は当初、逆井氏が築城、
戦国時代には北条氏が支配するところとなり、支配後の別名を飯沼城とも。
北条氏が築城し直したということもあり、ところどころに北条流築城技術が垣間見えます。

さっそく目の前に姿を現した遺構の数々。
手前に見えるのが二層櫓。そして左奥に見えるのが井楼矢倉(せいろうやぐら)です。
それではいきなりですが、このあたりの様子を動画でご覧ください。
手前に見える空堀も結構な深さで、
それだけでも目を奪われます。。
そして堀の上にかかる見事な橋。
ここからまずは、二層櫓を検分にまいります🔥

うん、見事な構え。
戦国時代の櫓は、城によっては半ば以上、天守の代わりともなっていたようです。

これが、門の内側から見た橋の様子です。
すべてしっかりとした木で形作られ、これだけでも見ごたえ十分と思えてしまいます。

正面から見た二層櫓です。
中に入ることもできます。
せっかくなので、靴を脱いでお邪魔します!

二層櫓の中はこのような造りになっています。
ここも動画に収めましたので、ご覧ください。
ご覧のように、中は結構な広さがあります。
割と角度が急な階段が上まで続いていて、気をつけないと足を滑らせそうな。。
最上階まで登ってみましたが、木窓は残念ながら動かせませんでした。
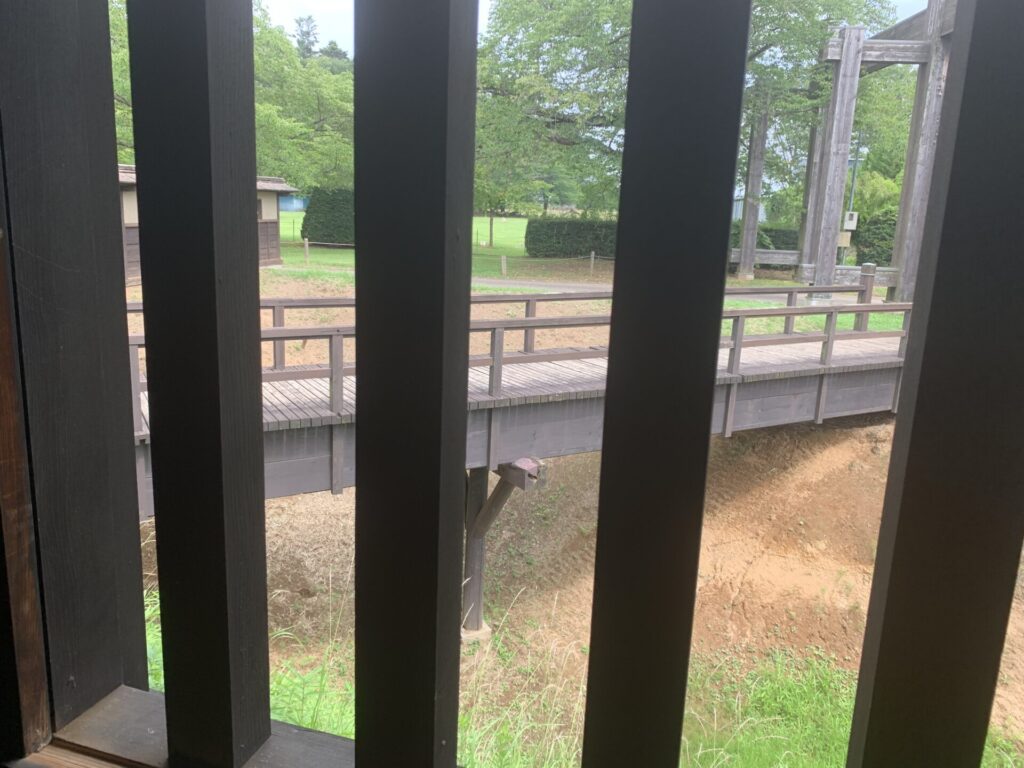
木枠から外の空堀をのぞいてみた写真です。
こういったアングルを楽しむこともできます。
これまた高さのある井楼矢倉(せいろうやぐら)にも登ってみた!!
二層櫓の検分を楽しんだあと、
続いて同じ塀沿いにある井楼矢倉(せいろうやぐら)にまいります✊

二層櫓から右に、塀沿いに進むと、すぐに井楼矢倉(せいろうやぐら)が見えてきます。

ここもまた、結構な高さですね。。
この上にも登ってみます🔥

この説明板にもあるように、
戦国当時の矢倉は、のちの天守閣の前身とも言えるもので、
高所から敵味方の動静を探るだけでなく、城における象徴的な役割(シンボル)も含まれていたようです。
ここに登る様子も動画でご覧ください。
下から見上げた時もそうでしたが、
上まで登ってから下を見下ろすと、
なおさら高さを感じることと思います。
これなら、敵味方の動きを把握できますね。

一番上に登ったところの写真です。
この板は敵兵の矢から身を守るためのものでしょうか。
本丸ともいうべき主殿に前身!!
ここから城跡の外郭沿いに進んでいき、
ぐるっと回って二層櫓の隣にある主殿に前身します。
城の本丸に該当するところ、ですね。

井楼矢倉(せいろうやぐら)を降りて、
土塁が広がる道を進んでいきます。
この城跡は、本当に土塁がしっかりと周囲に張り巡らされています。
この土塁たちを眺めるだけでも、城マニアにはたまらないと思います。

土塁の上に登ってみた様子です。
外側(写真の左側)から攻め登るには結構な高さがあることが分かります。

土塁を奥まで進んでくると、
このような、虎口(こぐち)のようなものに遭遇。。
虎口(こぐち)とは、、
城兵が城内に入る小さめの出入り口で、敵兵が侵入しにくいように、
道幅を狭くしたり、左右の土塁の上から狙い撃ちしやすく工夫した防御施設です。

そこから、道沿いに少し登ってくると、

道を右に折れたところで、最初の二層櫓の前に出てきます。
主殿は、その手前にあります。

このように立派な構えの城門を通過し、
主殿の中に足を踏み入れていきます。
ここの様子も動画でどうぞ。
二層櫓との位置関係がよく分かるかと思います。
庭の造りも、京都を思わせるような感じがして素晴らしいです✨
ご覧のように、戸板は開けることはできますが、開けたところで何も見られません。。
北条氏の代表的築城技術である角馬出から二の丸へ!
主殿を検分した後は、
さらに公園の奥の方へ進んでみます。

ここには何も説明板らしきものがなかったのですが、
この形状から考えて、ほぼ間違いなく、
北条氏が得意とする築城技術、角馬出(かくうまだし)でしょう。
角馬出(かくうまだし)とは、、
敵兵が細い道を伝って城内に侵入してくるところを迎撃するため、
城兵がその準備を整えやすくした防御施設のことです。
いやぁ、これだけ形がくっきりと残っていると、見ごたえありますね。。
ここの様子も動画に収めました。ご覧ください。
最初に二層櫓が奥に見えますので、これでおおよその位置関係もお分かりかと思います。
そして角馬出(かくうまだし)の手前に見える細い小道。。
敵兵がここから侵入してくるところを、
この角馬出(かくうまだし)で待ち構えて一気に迎撃しようというところでしょう。
周りを囲む空堀もくっきりと残ってますね。

それでは、先ほど見えたこの小道を通って、さらに奥へ。。

小道を通ってくると、木々に囲まれた、やや広めの場所に着きました。
奥に祠のようなものがありますし、主殿(本丸)との位置関係から推察するに、
ここはおそらく二の丸(二の曲輪)に該当するところでしょう。
ここの様子も動画でご覧ください。
すぐ近くには、またも櫓のようなものが見えます。
その方向に前身してみると、、
橋が渡してあり、割と深めの空堀がありました。

こちらがその橋です。
かなり立派な造りですよね。。
この下に空堀が見えます。

ご覧のように、ここもしっかりと空堀の跡が残ります。
公園の奥に、このように防御施設が見られるとは。。
城跡の”穴場”って、こういうところをいうんですよ。いや面白い!!
三の丸、そして比高二重土塁に感動!!
先ほどの橋を渡り切ったところに、
さらに大きな広場がありました。

ここも特段、説明板らしきものはありませんでしたが、
これまでの主殿、二の丸との位置関係から考え、ここはおそらく三の丸(三の曲輪)と思われます。

そして奥にはまたしても土塁の跡が。。
ここまで防御施設を見せつけてくれるとは、、ありがたいです。

三の丸(三の曲輪)(あくまでも推測)を北側の奥まで進んでくると、、

このように開けたところに。。
目の前にあるのは飯沼でした。
逆井城の北の防衛ラインですね。

そこから南側に歩いていくと、
ここもある程度の広さがあります。
しいて言えば、”外曲輪”とでも言いましょうか。。
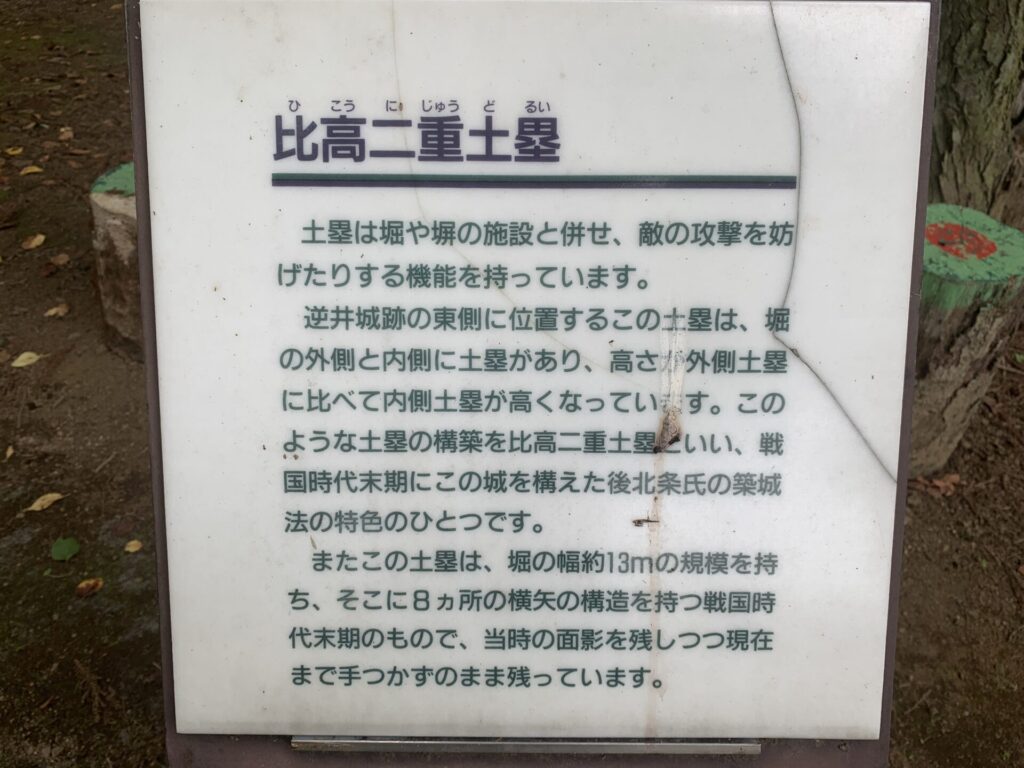
少し歩くと、このような説明板を発見しました!!
比高二重土塁!?
初めて目にする防御施設です。
いや驚きました。。
北条氏はまだまだこのような築城技術を持っていたのですね。。
この比高二重土塁の様子も、動画でご覧いただきたいと思います。
確かに、、
手前の外側の土塁に比べて、奥の内側の土塁の方が若干高めです。
最も、戦国の当時はこれよりもっと高さがあったのでしょうが。。
ここもまた、土塁の跡がくっきりと残り、驚きと感動ばかりです!!
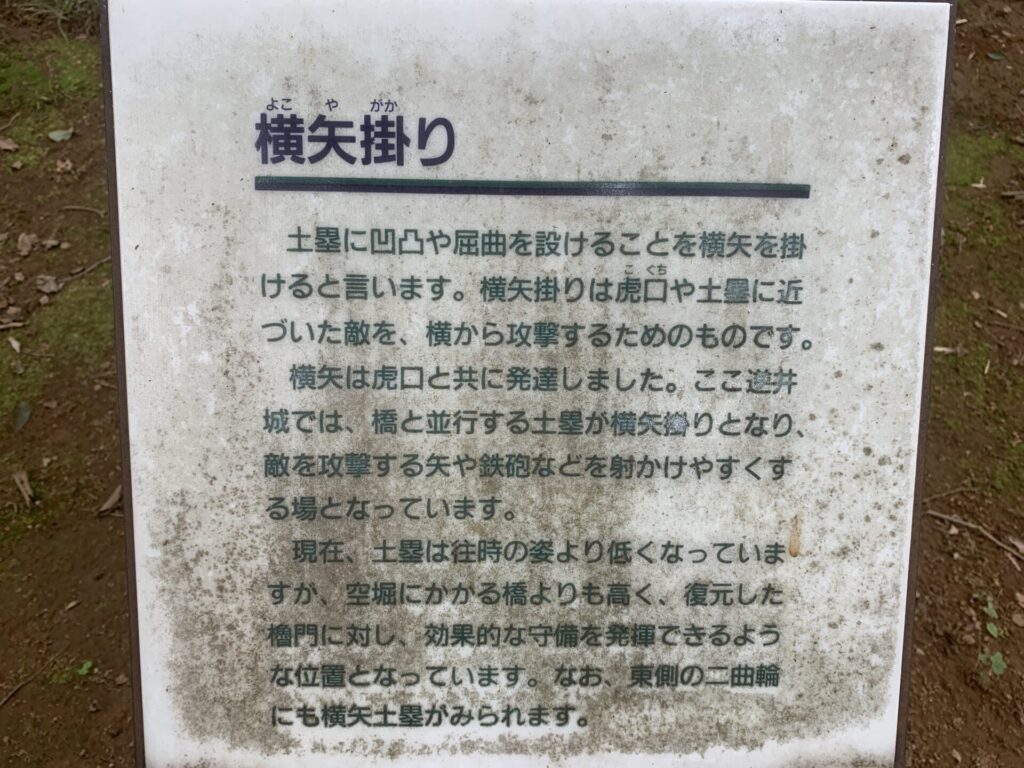
さらにさらに!!
横矢掛りという、城兵の防御戦法まで紹介した説明板もありました!
横矢掛りそのものは知っていたのですが、
こうして改めて紹介したものに遭遇すると、やっぱり嬉しくなりますね、城マニアとしては。。

木々に隠れて、奥の橋が見えづらいですが、、
この土塁上に登り、敵兵が橋を渡るところを側面から弓矢で狙い撃ちにするのですね。
次に、この空堀の中を歩いてみました。この様子を動画でご覧ください。
今ではだいぶ土が埋もれているので、そこまで高さはありませんが、
戦国当時は両側の土塁ともにかなりの高さがあったはずです。
まあ、これだけ形が残っているだけでもありがたい話ですが、、。

それでは最後に、この橋を渡って帰ります。
敵兵が順に、本丸を目指して攻め寄せていくイメージですね。

右側に見える三の丸(三の曲輪)と思われる広場を横目に見ながら、、

角馬出のある場所まで戻ってきました。
この角度から眺める馬出もまた見事です。

最後の最後に、二層櫓を見直し、逆井城とはお別れしたいと思います。
いや正直、この手前に目立つ二層櫓や井楼矢倉(せいろうやぐら)に目を奪われていましたが、
さらに奥の方に、とてつもない北条氏の防御施設が隠されていましたね。。
これだから、公園内の城跡は侮れないですし、絶対見落とすべきではありません。
一見、ただの公園の広場のようでいて、実は奥の方に、城跡の遺構が残っていたりします。
他に、似たような”隠れ城跡”としては、千葉県の国府台城(こうのだいじょう)があります。
こちらも一見、ただの公園なのですが、奥側に立派な石垣や土塁が隠れているんです。
ではでは、またの記事でお会いしましょう!!













